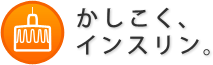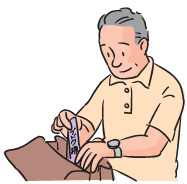
インスリンは膵(すい)臓で分泌され、肝臓から血流にのって全身に送られる過程で、インスリンに感受性のある肝臓、筋肉や脂肪組織の細胞に存在するインスリン受容体と結合し、ブドウ糖の細胞内への取り込み、細胞のエネルギー源としての利用、グリコーゲンや脂肪としての貯蔵促進などに働くのです。
食事として摂取された炭水化物は、身体にとってのエネルギー源となるブドウ糖に分解されます。
ところが、インスリンを産生する膵臓のβ細胞が正常に機能しなくなると、インスリンが適切に産生されず、身体の細胞は、エネルギー源となるブドウ糖を取り込めなくなります。
細胞内に取り込まれないブドウ糖は血液中にとどまり、細胞内ではブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなります。さらに、血液中のブドウ糖が増えることで、血糖値が上昇します。
糖尿病になり、この状態が長く続くと、細胞のエネルギー不足によるいろいろな症状が出現します。また、高血糖状態そのものが、血管を含め全身組織の細胞にいろいろな障害を与えます。
さらには、血糖値が非常に高くなると、腎臓がブドウ糖を尿に排泄しはじめます。頻回の排尿に伴い、脱水による脱水、倦怠感、喉の渇きなどの症状が現れます。体重も減少することがあります。
糖尿病を治療しないままにしておくと、長期間の高血糖による代謝障害などにより慢性合併症を引き起こす可能性があります。慢性合併症は全身のあらゆる場所に起こりますが、特に網膜症、腎症、神経障害などの細小血管症と、脳卒中、心筋梗塞・狭心症なあどの大血管症があります。
このように、インスリンは、細胞がブドウ糖をエネルギーとして利用するのを助け、適切な血糖値を保つ大切なホルモンなのです。